脱水は腎臓病の大敵!

こんにちは、純炭社長の樋口です。
地球温暖化の影響なのか、熱中症対策の話題で持ちきりですね。
浮腫みがない限り、腎機能を守るためには、とにかく”脱水”にならないように水分摂取を・・・と耳にタコが出来るくらい言われているとは思います。でも、「一日にどれくらい水分摂取ができているか」をどう計算するかご存知ですか?
水分摂取量の計算方法

『病院の栄養士から、1日の水分摂取は1~2Lが目安』と言われると思いますが、正しく計算はできていますか?
さて、水分摂取の中には、以下の物は含む?含まない?どちらでしょうか?
| 薬を飲むときの水は含まれるの? |
| 味噌汁やスープなど食事に含まれる水はどうなの? |
| 栄養ドリンクも含めてよいの? |
| コーヒーやお茶で摂ってもよいの? |
| アルコールを摂取した場合は? |
このようなものすべてを”水分摂取量目安の2L”に含めて良いのでしょうか?
どれが水分摂取に該当?

水分摂取量をはかるときのルールは2つあります。
| 1) | 食事の際の水分は計算に入れないください。 |
| 2) | カフェインやアルコールが入っている場合は計算から除外してください。 |
一般的に人間は1日に2.5 L程度の水を尿や汗などで失います。一方、食事から約1 Lの水分が補われ、体内でも約0.3 Lの水が作られます。
したがって、最低でも1.2 Lの水を食事以外から補給する必要があります。
(食事の内容や回数によって水分補給量は違ってきます)
※但し体に浮腫みが出ている場合は医師による水分摂取量の指導をきちんと守りましょう。
注意したい飲み物

コーヒー、紅茶、緑茶など、カフェインを含む飲料は利尿作用で水を失う原因になるので、計算には入れません。また、アルコールを飲んだ場合も脱水作用があり、摂取する以上の水分が失われてしまいます。その他、注意したい飲み物をまとめました。
| カフェインの多いお茶やコーヒーを飲む場合 | チェイサーとして水を飲んだり、ノンカフェインのお茶(麦茶・番茶・ルイボスティーなど)や、カフェインレスのコーヒーなどを利用してみましょう。 |
| アルコールの入ったお酒を飲む場合 | アルコールを体内で分解するときに脱水状態になります。お酒と同等かそれ以上の量の水を和らぎとして飲むようにしましょう。 |
| 甘味のついたドリンクを飲む場合 | 経口補水液やスポーツドリンクなど甘味や塩分が入ったものは、飲み過ぎると腎臓に負担がかかりますのでなるべく控えた方がよいでしょう。甘味のついたジュース類も血糖値を上げて腎機能を低下させる原因となりえます。 |
腎臓に一番やさしい飲み物はやはり、水や白湯です。
コーヒーやお茶はダメではない

余談になりますが、1日にコーヒーを4杯以上のむと死亡リスクが低下するという結果が報告されています。
死因別では、心臓病・呼吸器疾患・脳卒中・糖尿病・感染症などの死亡リスクを低下させるばかりか、驚くべきことに外傷や事故といった病気以外の死亡リスクまでも低下させると言うのです。慢性腎臓病でもコーヒー摂取が死亡リスクを低下させるという報告があります。
関連ブログ:腎臓に良い食べ物コーヒー編
コーヒーの健康成分も活用しよう
この作用はインスタントコーヒーやカフェインレスコーヒーでも認められることから、カフェインが効いているのではなく、コーヒーに含まれるクロロゲン酸などのポリフェノール類による効果だと考えられています。
コーヒーを楽しんだ後は
ただし、前述したようにカフェインを含むコーヒーには利用作用があって尿として水分が失われてしまうので、少なくともコーヒーの2倍の量の水を補った方がよいと思います。
水分摂取アプリを活用

スマートフォンやタブレットを使っている人は水分補給サポートアプリを使ってみてはいかがでしょうか。
『水分補給 アプリ』等と検索すると色々出てきますよ。
一日分の目安量が計画的に摂取が出来るようサポートしてくれます(一気に飲まずにちびちび飲むのもコツ)
おわりに

純炭粉末公式専門店スタッフのゆっきーもアプリで水分摂取量を管理しているそうです。『〇時までにあと〇ml!あなたならできる!』と促され励まされ・・・(+o+)アプリに従って飲むようになったら、日頃、喉が渇いてないからと、いかに水分摂取が出来ていなかったかが目に見えて分かるようになったとか。
脱水は腎臓病だけではなく命取りになりかねません。また、脱水は夏だけの問題ではなく、冬場の隠れ脱水も問題視されています。「喉が渇かないから」とか「夜トイレに行きたくないから」と水分摂取を怠ってしまうのが原因です。そんな時こそアプリを使ってこまめにチビチビ水分を摂取するのがおすすめですよ。
熱中症の腎臓病対策には、関連ブログ:『梅雨明け直後の熱中症にご用心』も併せてご覧くださいね!
【純炭粉末公式専門店】は→こちら


























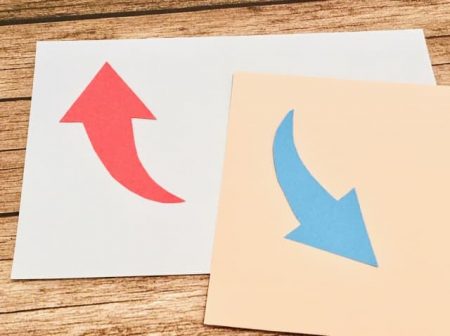



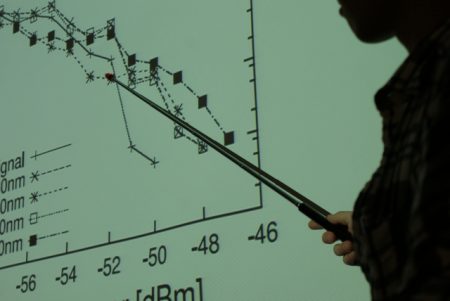









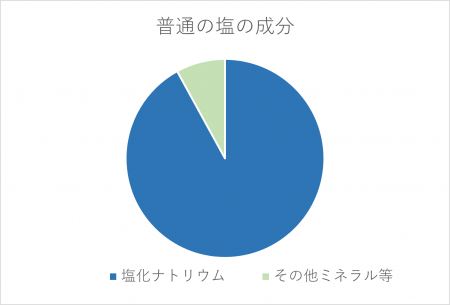
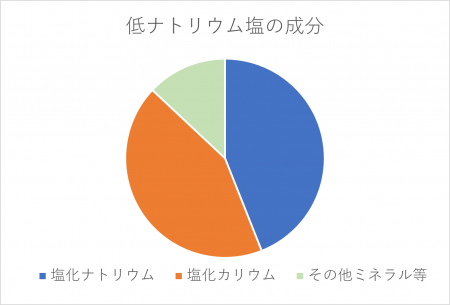




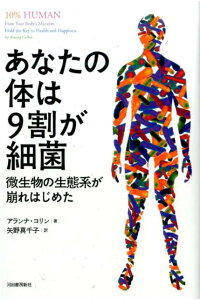










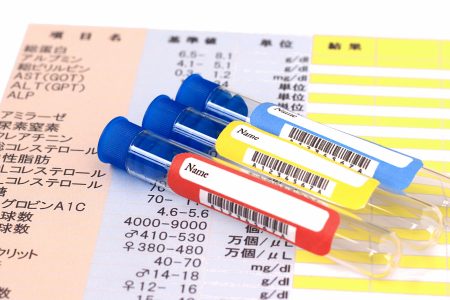





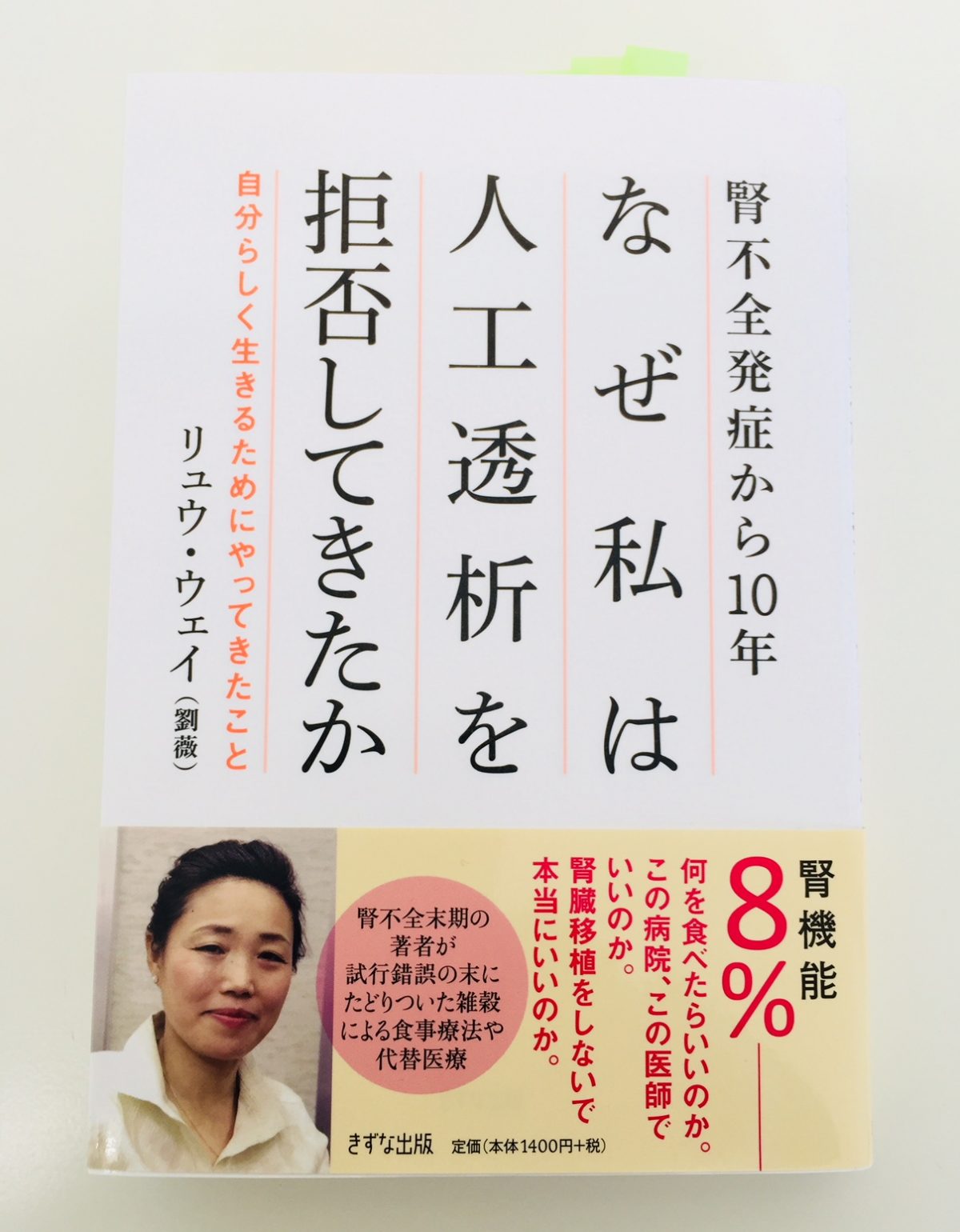
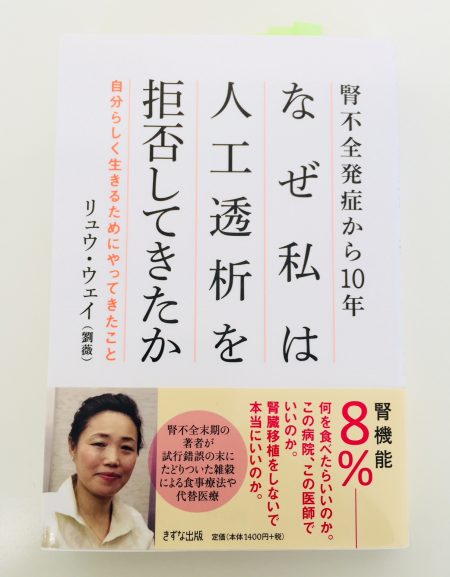





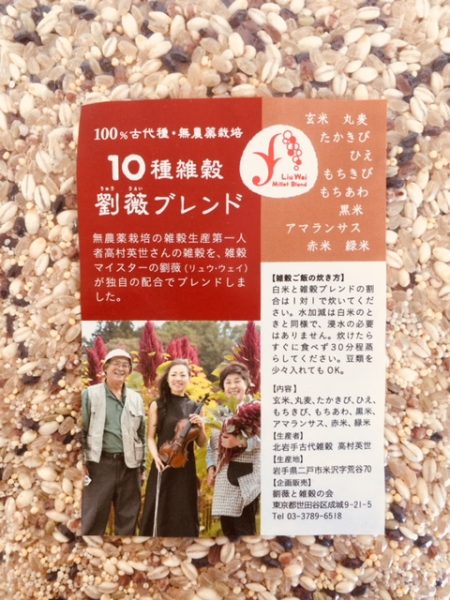












最近のコメント