新薬の最新情報や、糖尿病・アルツハイマー病の話題をご紹介します

目次
慢性腎臓病の新薬や治療法の最新情報をお届けします

毎回きよら通信を読んで下さる健康意識が高いあなたへ、腎臓病や糖尿病、アルツハイマー病に関する新情報をお届けします。
早速チェックしてみて下さいね。
【ニュース1】SGLT2阻害薬とMR拮抗薬の併用は単剤よりも腎保護効果が高い
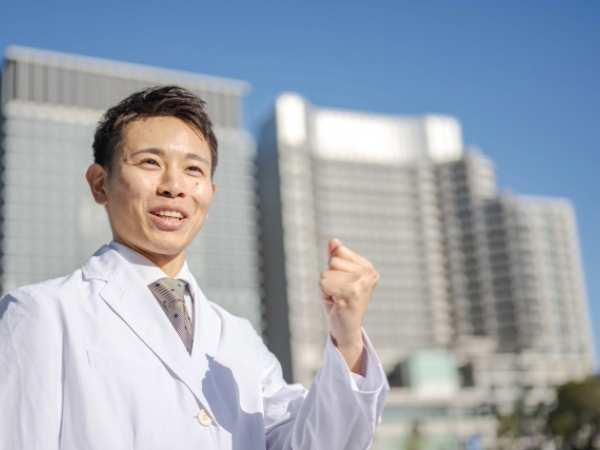
SGLT2阻害薬(商品名フォシーガ、カナグル、ジャディアンスなど)とMR拮抗薬(商品名ケレンディア)は、それぞれ腎機能の低下を緩やかにする腎保護効果が認められています。
2025年6月に開催された欧州腎臓学会議では、両薬剤を併用した場合に腎保護効果が更に高まることが報告されました。
2型糖尿病を合併した慢性腎不全患者を
①ジャディアンスのみ服薬
②ケレンディアのみ服薬
③ジャディアンスとケレンディアの両方を服薬
の3グループに分けて、180日後の尿蛋白変化量(尿中アルブミン/クレアチニン比)で腎機能を比較しました。
その結果、①ジャディアンス単独では-29%改善、②ケレンディア単独では-32%改善だったのに対して、③ジャディアンスとケレンディア併用では-52%も改善が認められたとのことです。
気になる併用時の副作用も、単剤の時と変わりがなく、併用療法への期待が高まります。
【ニュース2】大塚製薬がIgA腎症に対する新薬を開発中。有効性を確認!

IgA腎症とは、IgA(感染防御に必要な抗体の1種)に対する自己抗体ができてしまう病気です。
免疫複合体というたんぱく質の塊が、腎臓のろ過装置(糸球体)にへばりついて炎症を起こし、腎機能が低下します。
IgAは、体内に侵入しようとする病原体や毒素を捕まえて排除してくれる頼もしい存在ですが、IgA腎症では糖鎖欠損IgA1という異常なIgAを作る免疫細胞が増えてしまっています。
糖鎖欠損IgA1は、本来は体の中に存在してはいけない異物なので、正常な免疫細胞が糖鎖欠損IgA1を攻撃する抗体を作るようになる訳です。
大塚製薬が開発中の新薬は、異常な糖鎖欠損IgA1を作り出す免疫細胞を抑える薬です。
腎臓の目詰まりや炎症を減らして、IgA腎症の進行を抑制してくれる作用が期待できます。
2025年6月に開催された欧州腎臓学会議で、尿蛋白を改善する明確な効果が発表され、現在は米国で優先審査を受けているとのことです。
この新薬によってIgA腎症から透析に入る患者がゼロになることを願っています。
【ニュース3】ネフローゼ症候群の原因である膜性腎症の治療薬がフェーズ3の最終段階へ

膜性腎症は、尿中にたんぱく質が大量に漏れ出すネフローゼ症候群の主な原因になる病気です。
腎臓のろ過装置である糸球体に、PLA2Rというたんぱく質が存在します。
膜性腎症では、PLA2Rに対する自己抗体が出現して、ろ過装置を破壊してしまい、本来はろ過されないアルブミンなどのたんぱく質が尿中に漏れ出してしまいます。
バイオジェンが開発中の新薬は、問題となる自己抗体を作り出すCD38陽性細胞に対して、攻撃を仕掛ける抗体医薬です。
この新薬の開発が成功すれば、ろ過機能の破壊を抑えられるので、ネフローゼの患者が大幅に減少することでしょう。
【ニュース4】慢性腎臓病の早期から生じるうつ病リスクに注意

末期の腎臓病ではうつ病を併発しやすいことが知られていますが、軽度(eGFR60を切るくらい)の腎臓病患者でも、うつ病のリスクが上昇することが東大医学部から報告されました。
「最近気分がスッキリしない」、「食欲がない」、「やる気がでない」などと感じたら、腎機能(eGFRやクレアチニン、尿蛋白など)をチェックしてみましょう。
朝日を浴びる・軽い運動・笑う・人と会ってしゃべる・瞑想・自然に触れる・・・など、手軽にできる方法で、精神面の健康を保つ習慣を意識すると良いですよ。
【ニュース5】糖尿病薬『メトホルミン』が寿命を延ばす可能性

アメリカの研究によると、メトホルミンを使用した閉経後の女性は、他の糖尿病薬を使用していた患者に比べて、90歳未満での死亡リスクが30%も減ったとのことです。
近年では「老化は病気の一種」と考えられており、老化を治療するための薬剤や治療法が盛んに研究されています。
100歳を超えても若々しく活躍できる世の中が来るかも知れません。
【ニュース6】ワクチンで認知症が予防できる?アルツハイマー病の原因に新説が浮上!

腎臓病とは無関係ですが、誰もが避けたい認知症“アルツハイマー病”の最新の知見です。
これまでアルツハイマー病の原因は「アミロイドβ」や「タウ蛋白」といった脳のゴミが神経細胞周辺に蓄積することで起こると考えられていました。
ところが、脳のゴミ説の発端となった有名な論文に捏造があったことが発覚し、別の発症メカニズがあるのでは?と囁かれているのです。
実は、帯状疱疹やインフルエンザ、肺炎に対するワクチンを接種すると、認知症の発症リスクが30~40%も低下することが知られています。
このことから「認知症の原因は感染症による炎症ではないか?」との新説が浮上しているのです。
つまり、感染症だけでなく怪我による炎症も、まわりまわって認知症に進展する可能性があります。
炎症を避けるために、ワクチンを賢く利用したり、抗炎症作用が期待できる薬を使うなどの方法で、世界中で増加し続ける認知症患者を減らすことができるかも知れません。
〜帯状疱疹ワクチン体験談〜

先日、純炭社長やゆっきーの両親は、帯状疱疹のワクチンを接種してきました。
このワクチンは1回接種の『ビケン』と、2回接種の『シングリックス』の2種類から選択できますが、10年以上も効果が持続するシングリックスをチョイス!
ゆっきー両親は接種後の副反応はありませんでしたが、純炭社長は倦怠感(接種部位の痛みや発熱、頭痛など)が出たそうです。
はたして本当に認知症予防効果があるのか?
注意深く観察し続けたいと思います(笑)。
(2025年10月号として配布したものです)
![]()
- この記事を書いた人
- ゆっきー
美味しいものを食べることと、山登りが趣味の”ゆっきー”です。
きよら通信やブログはゆっきーがお届けしています。
また、お電話で商品をご注文のお客様は”ゆっきー”が電話対応させていただくことも。お客様に安心してご購入いただくことを信条としていますので、ご相談から世間話までお気軽にどうぞ♪いつも元気と笑顔がモットーです( *´艸`)

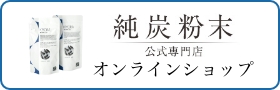

「新薬の最新情報や、糖尿病・アルツハイマー病の話題をご紹介します」への2 件のフィードバック
ゆっきーさま
GIに関する質問です。
果糖は血糖値が急激に上昇しやすいので注意が必要との情報で食品の裏面で果糖より砂糖やぶどう糖入りを優先していますが下記のデータを見つけました。
果糖は砂糖やぶどう糖より悪質なんでしょうか?
2.糖類のグリセミックインデックス(GI)の一例
糖類名 GI値
ショ糖 68
果糖 19
糖類名 GI値
乳糖 46
(ブドウ糖) 100
上記は下記サイトのこぴーです。
http://www.kudamono200.or.jp/number/answer_08.html
鋭い視点からの質問ありがとうございます。
GI値は「血糖値を上げる程度を示す値」であることは良く知られています。
ブドウ糖を100とした場合、果糖のGI値は19なので、果糖は血糖値を上げにくい…というのは本当です。
駄菓子菓子、大きなトリック(或いは誤解)が存在します。
そもそも、血糖値というのは血液中のブドウ糖濃度を測定しているだけで、果糖濃度は測定していないのです。
ですから腸管から果糖が吸収されても血糖値としては測定されません(果糖の一部がブドウ糖に変換されるのでGI値が19になります)。
ショ糖(砂糖の主成分)はブドウ糖と果糖が1:1で結合した物質です。
仮に100分子のショ糖を食べたとすると、小腸で50分子のブドウ糖と50分子の果糖に分解されます。
血糖値測定器はブドウ糖しか測定できないので、50分子のブドウ糖と果糖から作られる18~19分子のブドウ糖を測定し、ショ糖のGI値が68になるとお考え下さい(実際には果糖がブドウ糖に変換されるタイムラグがあると思いますが、ここでは話を単純化しています)。
次に「果糖は砂糖やブドウ糖よりも悪質か?」にお答えします。
私の考えではイエスです。
理由を説明する前に、そもそもGI値が高い(血糖値が上がりやすい)食品が嫌われる理由を考えてみたいと思います。
人間の全血液中には角砂糖1個分(4~5グラム)のブドウ糖しか存在しません。
ところが、食事を摂ると血糖値が急上昇します(GI値が高い食品ほど血糖値を上げやすい)。
高血糖は体にとって緊急事態なので、インスリンというホルモンが血液中のブドウ糖を筋肉などに取り込ませて、血糖値が低下します。
ところが、インスリンに問題が生じて高血糖状態が長く続くと(糖尿病状態)、様々な症状(腎症・網膜症・神経症・足の切断など)が現れてきます。
この様な症状は高血糖による血管障害によって発症するもので、血管のAGE化やAGEによる炎症・酸化ストレスが原因(のひとつ)と考えられます。
そこで、AGEができにくい(血糖値が上がりにくい)低GI値食が健康食として推奨されるわけです。
さて、果糖を摂っても血糖値の上昇はわずかです。
しかし、果糖はブドウ糖の10倍もAGEを作りやすく、しかも毒性の強いAGE(メチルグリオキサール由来AGE)を作ります。
AGEの観点から考えると、果糖はブドウ糖よりも悪質と考えられます。
だからと言って果物などを否定するわけではありません。
新鮮な果物はビタミン類も豊富で健康に良いことは言うまでもありません。
但し、「果糖は血糖値が上がりにくいので食べ過ぎても大丈夫!」とは考えないでくださいね。
また、清涼飲料水などに使われている果糖ブドウ糖液糖は吸収が早く、AGEや脂肪になりやすいのでご注意ください。