こんにちは、純炭粉末公式専門店 店長のたっくんです!
前回の学会レポート『腎臓病とマグネシウムについて』では「マグネシウムが慢性腎臓病の血管石灰化(血管にカルシウムが沈着して、もろい骨のように折れやすくなる危険な状態)を予防するかもしれない」という新たな可能性についての研究を紹介しました。
今回のテーマは、血管をもろくしてしまう原因物質のひとつ、リンについての研究レポートをお伝えします。
リンっていったい何?

リンとは体内のミネラルの中でカルシウムの次に多い栄養素。
その85%がカルシウムやマグネシウムとともに骨や歯をつくる成分になり、残りの15%は筋肉、脳、神経などの様々な組織に含まれ、エネルギーをつくり出す時に必須の役割をしています。
魚、乳製品、大豆、肉といった動植物性のたんぱく質には有機リン(注1)が多く含まれていて、現代の食生活では一般にリンが不足することはありません。むしろ、食品添加物や加工食品の中に含まれる無機リン(注2)によって、過剰摂取になっているのでは?と心配されている状況です。外食や加工食品に偏りがちな場合は、リンの摂り過ぎに注意しなければいけません。
注1:有機リンとは細胞膜や核酸などに結合しているリンで、吸収率は無機リンよりも低い。
注2:無機リンとは食品添加物のように食品に添加される薬品としてのリン。
リンはこんな悪さをする

最近、研究が進められているCPP理論というものがあります。体内が高濃度のリンにさらされるとCPPというものができます。CPPとはCalciportein Particles(カルシプロテイン パーティクル)の略で、リン酸カルシウムFetuine-Aというたんぱく質が反応してできた、トゲトゲの結晶構造の事です。このトゲトゲが全身の血管を傷つけ、血管石灰化を引き起こす原因となっているという仮説の事を言います。(※1,2)
腎臓でも悪さをします
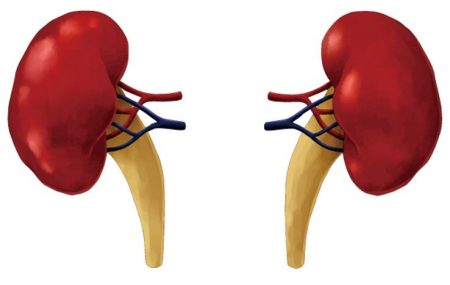
トゲトゲの結晶は腎臓でも悪影響を及ぼします。腎臓のどこで悪さをしているかというと、血液中の老廃物を濾過する糸球体の直後にある近位尿細管という場所です。通常、過剰なリンは糸球体からすぐに排泄されますが、排出される出口は、高濃度のリンにさらされるため、トゲトゲのCPPがたくさん作られて、ダメージをうけてしまうのです。
尿細管障害は糸球体傷害とは異なり、尿検査はわからないという特徴があります。
未然に防ぐ方法は

トゲトゲのCPPが作られる反応は高濃度のリン負荷から始まりますが、自分がリンの過剰摂取なのかどうか?は、残念ながら血液検査では分かりません。なぜなら、血中リン濃度は厳密にコントロール(管理)されていて、腎機能が相当悪くならないと血中のリン濃度に異常をきたさないからです。腎機能がある程度はたらいていれば、尿中にリンを排泄できるので、血清リン濃度は正常域を超えることはまずないという訳です。
であれば、同時に尿検査を受ければわかるのでは?と思われるかもしれません。
確かに尿中リン濃度は測れますが、残念ながら通常の検査項目には含まれていません。
また、食後や無機リンを多く摂取した後など、採尿のタイミングで測定値が大きく変化してしまうため、正確な判断がし難いという欠点もあります。
まとめ
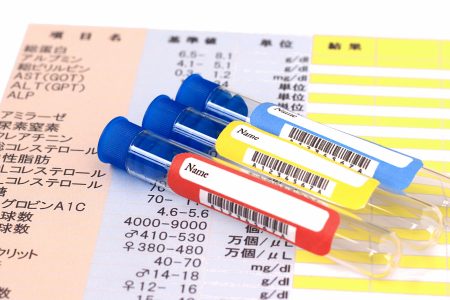
・食事からのリン過剰摂取が血管の石灰化を引き起こす。
・体内で一番リンの被害が大きいのは、余分なリンを排泄する尿細管の部分。
・血液検査ではリン負荷を見るには適していない。
・血液検査でリンが正常値であっても、密かに石灰化が進んでいる場合もある。
では、どうしたら良いのでしょうか。ここからは腎臓病ではない健康な人にもあてはまる話です。
とにかく「食品から摂りこまれる無機リン(添加物としてのリン)に注意」
避けるのはたんぱく質に含まれる有機リンではありません。むしろ無機リンに注意してたんぱく質は積極的に摂取したほうが生命予後が良いというデータもあります。(※3)
検査値では見えにくいリン負荷、だからこそ何にリンが多く入っているかを把握、自分で意識しなくてはなりません。
だからと言って、一日何mg以下に抑えなきゃ・・・と神経質になるとストレスが溜まって腎血流量が減ってしまいます。
でも、大丈夫!
食事中のリン含有量を意識するだけでも石灰化が抑えられた!という結果もあるようなので、以下に紹介する注意点を読んで、ちょっとだけリンに意識を向けてみてくださいね。
避けるべき食品

この食品を減らすだけでずいぶん違う!具体的なリンの見分け方についてです。
スーパーに行って、ハムやソーセージ、お惣菜の成分表示を注意深く眺めても、「リン」や「リン酸」という言葉が書かれているのは稀です。こまったことに、リンは食塩(ナトリウム)のように含有量の表示義務がないのです。さらに厄介なのは、食品表示を巧妙に書き換えて、無機リンが添加されていること。
食品を買うときには、裏面(原材料表記)を見る癖を付けて、以下の表示がある食品には、吸収率の高い無機リンが添加されている(可能性が高い)ことを意識するようにしましょう。(※4)
| リンから体を守るために避けるべき食品 | ||
| 安い加工肉(ハム・ソーセージなど) | 保存料・PH調整剤・増粘剤・発色剤 | 見た目や保存性、味を向上させる為に無機リンを添加。 |
| 発泡酒、第3のビールなど | 各種添加物 | 旨味を出すために無機リンを添加。 |
| プロセスチーズ、乳製品など | 乳化剤、pH調整剤 | |
| 清涼飲料水(ジュース類、一部のお茶、紅茶) | 酸味料 | 風味を良くするため無機リンを使用。 |
| パンや菓子など | イーストフード、膨張剤、ふくらし粉、ベーキングパウダー | |
食品に無機リンを添加すると、美味しく感じたり、保存性が良くなったり、見た目も美味しそうに変化したりするのです。
なので、
ソーセージやハム、ベーコンが食べるなら、(ちょっと高価になりますが)なるべく保存料が少なくて、賞味期限の短いものを。
ビールなら生ビール。
チーズならナチュラルチーズ。
ジュースは・・・・これを期にやめましょう(笑)。砂糖や果糖ブドウ糖液糖も多いのでAGEができやすく血糖値も上がってしまいます。
食事は人生の幸福に大きく寄与しますから、ストイックに全部やめてしまう必要はないとおもいます(お金も時間もかかるので)。何を食べるか”質”を追求することも大切なんだな~と思う今日この頃です。
なんとなく毎朝ハムエッグを食べて、夜は節約のために発泡酒を飲む・・・・といった習慣をやめて、朝はゆで卵(添加物ゼロに加えてAGEも少ない!)、夜は3日に1度の生ビールにあらためようと心にちかう、たっくんなのでした。
参考資料
※1.東京農業大学の研究について
応用生物科学部栄養科学科での研究
食品添加物からのリンの大量摂取についての影響等を調べたもの。現在では食品添加物として多量のリンを摂取しており特に腎臓へのカルシウムが沈着(石灰化)の原因として問題となっているが、マグネシウム摂取によって腎石灰化抑制の可能性が少しずつ明らかになっている。
※2.自治医科大学の研究について
無機リンが慢性腎臓病に及ぼす影響についての研究。現段階では腎臓病の進展により血漿CPP(トゲトゲ)が増加するという結果が出ている。慢性腎臓病における腎障害や血管石灰化のメカニズムを解明する方法として血中CPP測定の臨床が注目されている。
※3.CJN.04620510 Epub 2010 12月9。
血液透析患者における規定の食事性リン酸塩制限と生存についての論文より。
身も蓋もない話になりますが、たんぱく質はしっかり摂って、もしリン濃度が上がってしまう用ならリン吸着剤の使用や、透析時間長くした方がずっと予後が良い(長生き)という研究結果があります。
※4.リン酸探検隊
食品中に無機リンがどれくらい入っているかを調べた外部リンク、わかりやすく解説されています。
【純炭粉末公式専門店】は→こちら






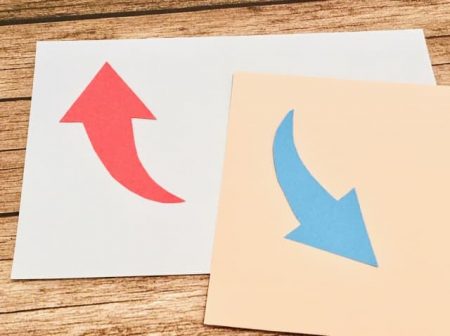



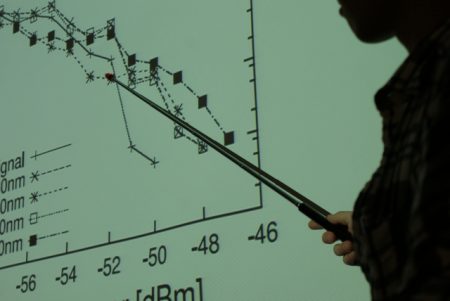


















最近のコメント