こんにちは「食べる純炭きよら」を製造販売している純炭社長の樋口です。
今日のブログはマイブームである糖質制限から離れて
私の妻の命を救ってくれたかかりりつけ医の女医さんの話を紹介しようと思います。
妻が40代後半に差し掛かった頃のことです。
健康診断で肝機能を示す数値に異常が現れました。
私と違って缶ビール一本程度しか飲まない妻は、
一切のアルコールを絶って再検査に臨みましたが、
何度検査しても異常値が出ます。
大病院の診察では原因不明。
そんな状態が2年ほど続いたでしょうか。
時を同じくして
・動悸、息切れ
・ほてり
・食べても食べても太らない
・寝ている時に足がつる
といった症状もあり、
「ちょっと早いけれど年齢的に更年期かな?」などと話していました。
ご承知のように女性の更年期は45歳~55歳に訪れ、以下のような症状が現れます。
8)頭痛、めまい、吐き気がよくある妻の症状も更年期障害に当てはまるものが多く、それほど心配はしていませんでした。ところが久しぶりに訪れたかかりつけの女医さんに診てもらったところ
「甲状腺機能亢進症」の疑いがあり、すぐに血液検査をしましょう!
となりました。
ここで、更年期障害と甲状腺機能障害の症状を比較してみましょう。
更年期障害 甲状腺機能亢進症
8)頭痛、めまい、吐き気 → → → 〇頭痛、めまい、吐き気このように両者の症状はとても良く似ているのですが、
甲状腺機能亢進症を治療せずに放置しておくと心不全で突然死を引き起こす
実は怖い病気なのです。甲状腺機能亢進症とは(いくつかの原因で)甲状腺ホルモンの働きが活発になりすぎる病気です。
甲状腺ホルモンは全身の細胞の働きを活発にするので、
・心拍数の増加(動悸)
・細胞の代謝亢進(ほてり、発汗)
・エネルギー消費の増加(食べても太らない、痩せる)
といった症状が引き起こされます。
妻の場合、大病院で放置されていたら今頃は心不全で亡くなっていたかも知れません。
幸いなことに甲状腺機能亢進症にはメルカゾール(一般名チアマゾール)という良く効く薬があります。
(メルカゾールは私の元職場である中外製薬の製品だったというのも何かの縁?)
メルカゾールで治療を始めたところ、
肝臓の異常値は無くなり、
(異常だった)食欲も低下。
動悸・息切れ・ほてりなどの症状も治まりました。
服薬を始めて数年になりますが、やっと薬から離脱できそうです。
更年期という言葉は女性も男性もあまり聞きたくない言葉なのかも知れませんが、
甲状腺機能亢進症のような突然死につながる怖い病気が潜んでいる可能性もあります。
ご自分もしくはご家族が動悸・息切れ・ほてりなどを訴えたら、
・食欲のわりに痩せていないか?
・肝機能に異常値はないか?
などに注意をはらって甲状腺機能亢進症を見逃さないで下さいね。
更年期を乗り切るためのイソフラボンに関する話題は
「豆乳や豆腐には反栄養素が含まれる?」からお入り下さい。
(甲状腺機能亢進症で糖質制限したらエネルギーが枯渇してとんでもないことになりますね)
↑※と書いてしまいましたが糖質制限とメルカゾールで短期間に甲状腺機能亢進症が治るという情報がありましたので追記しておきます(2014年11月28日)

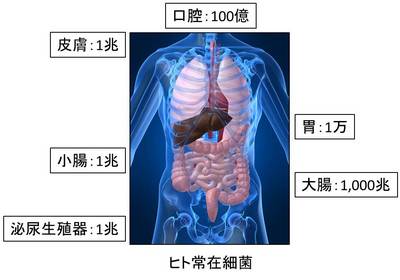
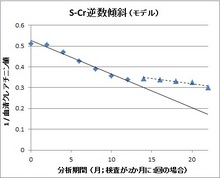

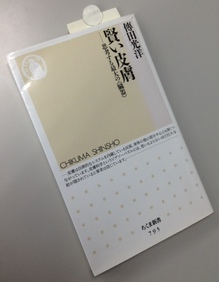
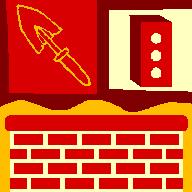 皮膚表面が「死んだ細胞」と,「細胞間脂質」からなること,死んだ細胞がレンガ,その隙間を埋める細胞間脂質がセメントみたいなイメージであることが示されていました。
皮膚表面が「死んだ細胞」と,「細胞間脂質」からなること,死んだ細胞がレンガ,その隙間を埋める細胞間脂質がセメントみたいなイメージであることが示されていました。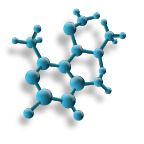 個々のアミノ酸の性質が違うので,ジペプチド,トリペプチドでもアミノ酸の組みあわせによっては電荷を持ったり油への馴染みの度合いが違ったりします。
個々のアミノ酸の性質が違うので,ジペプチド,トリペプチドでもアミノ酸の組みあわせによっては電荷を持ったり油への馴染みの度合いが違ったりします。

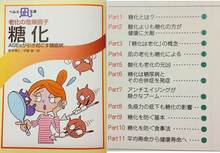
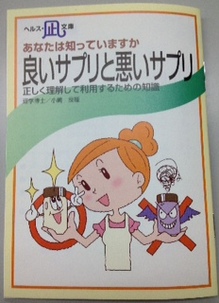











最近のコメント