こんにちは。
純炭社長@糖質制限中の樋口です。
カテゴリ「理系研究職の生き方」では9月に沼津東高校で行った「職業を知るセミナー」の内容や
生徒さんからの質問への回答などを書きつづっています。
今日の質問は、
「炭を食べるなどという想像もつかない発送、逆転の発想はどこから生まれましたか?」
中外製薬を退社したのち、金沢医科大学のベンチャー企業で働き出した私は
理科機器会社の社長が持ち込んだ炭に出会いました。
その社長は発熱体として炭を利用していましたが、
その炭を血液と混ぜて何が吸着されるか?を測定したところ、
クレアチニンや尿素窒素といった腎機能を示す数値とともに
リンの値も下がっていることに気付きました。
腎不全治療ではクレメジンという活性炭の薬と
リン吸着剤の2種類の薬が処方されます。
しかし、両方とも飲みにくい薬で便秘の副作用も強いという欠点がありました。
もし、この炭が本当にリンを吸着する能力があるのであれば、
今まで二つの薬を飲んでいた患者さんが一つの薬で済むようになるのではないか?
ところが、理科機器会社の社長が持ち込んだ炭は
中国産の布を原料に使っており、発がん性のある染料などが含まれている危険性がありました。
そこで、我々は竹、綿花、おがくず、海藻、コーヒーなど様々な材料を炭にして吸着実験を繰り返しました。
竹を電気炉で炭化させた際には、竹に含まれるカリウム元素が電気炉に残留してしまい、
その後に焼いた材料の表面にカリウムが付着するアクシデントにも見舞われました。
試行錯誤を続けて分かったことが三つありました。
一つ目は、リン吸着能を持つ炭には炭素の他にカルシウムが多く含まれていたこと。
二つ目は、炭化させる原料に含まれている物質(植物細胞に大量に含まれているカリウムや植物の生育環境に存在したと思われるヒ素や鉛など)は炭化させても炭の中に残留すること。
三つ目は、竹や木などの天然物を原材料にするかぎり、品質管理が不可能であること。
仮に竹を材料として炭を作る場合でも、産地が違えば竹に含まれる物質も違います。
また、同じ地域の竹であってもシーズンごとに組成が変わる可能性もあります。
農薬などが近くで使われれば残留農薬の心配もあります。
そこでたどり着いた原材料が
食品や医薬品にも使われている不溶性食物繊維の一種「結晶セルロース」でした。
「食べる純炭きよら」に配合されている純炭粉末は結晶セルロースを日本、米国、韓国で特許を取得している特殊製法で炭化した安心安全な炭なので、長期間安心してお飲みいただけるのです。


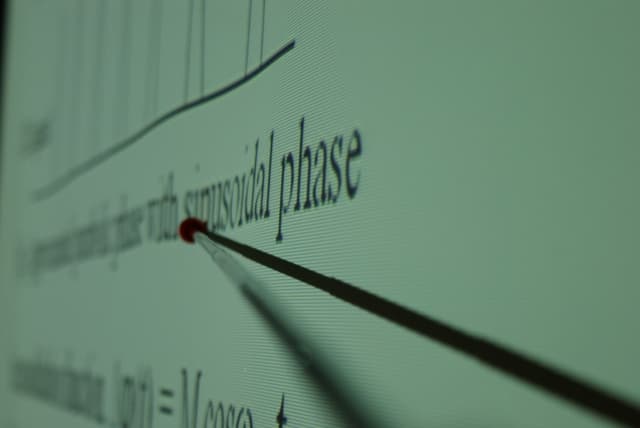
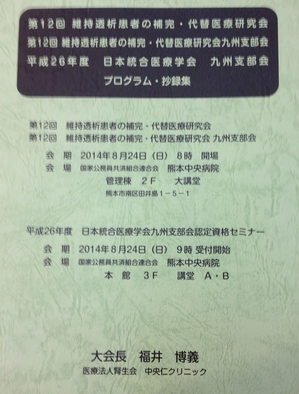
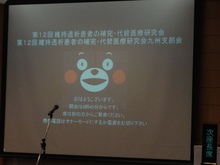














最近のコメント